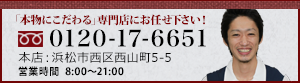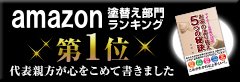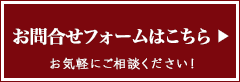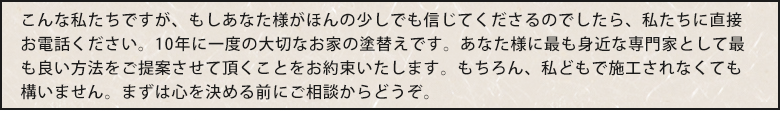第9回 塗装業者の選び方 -ステップ3《前編》-
- 2015年04月25日
こんにちは。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
株式会社 美匠代表の高橋と申します。今回のコラムでは、
外壁塗装・屋根塗装を行う際の塗装業者の選び方について
塗料の視点からお話させて頂ければと思います。-ステップ3 塗料から見る塗装業者の選び方《前編》-
塗装業者が使う塗料というのは何百種類もあるのですが、
大きく分けると下記のように分けられます。・アクリル塗料(耐候年数 約3年)
・ウレタン塗料(耐候年数 約5年)
・シリコン塗料(耐候年数 約10年)
・遮熱塗料 (耐候年数 約12年)
・断熱塗料 (耐候年数 約12年)
・フッ素塗料 (耐候年数 約15年)
・無機ハイブリッド塗料 (耐候年数 約20年)などが代表的な塗料の種類です。
この塗料の名前は、業者とお話した事があるお母さんお父さんでしたら、
おわかりになる方も多いのではないでしょうか。現在主流のシリコン塗料を例にすると多くの業者は、
「このシリコン塗料は15年は持ちますよ」と言う業者が多いのですが、一言でシリコン塗料と言っても耐候年数が
5年程度のものから13年程度のものまであるんです。塗料の種類や施工技術でこれだけの差が生まれてしまうのです。
塗料の種類が水性か溶剤(油性)なのか、1液型なのか2液型なのかによって、
まず耐候年数の差が生まれます。一番耐候年数の長い塗料の種類は、
何といっても『弱溶剤2液型』タイプの塗料ですが、この2液型塗料は、
一般的なホームセンターなどにも売っている1液型タイプの塗料と違い、
使う時に2つの液体(主剤と硬化剤)を1gも間違えないように混ぜて使う必要があるため、
業者も手間がかかるという理由で、1液型タイプの塗料を使うことが主流となっています。塗料メーカーに問い合わせをしても、
「1液型も2液型も耐候性はほとんど変わりません」
「水性も弱溶剤も耐候性はほとんど変わりません」と答えるメーカーが多いのですが、
実際に施工した現場を見れば一目瞭然で、
水性1液型で施工した現場と弱溶剤2液型で施工した現場では
色のツヤや色あせ具合に大きな差が出てきています。また、耐候性が変わらないのであれば、
環境のことも考えて、全て水性1液型塗料にすれば良いものの、
弱溶剤2液型で最新の塗料が次々と出てくる現状を考えると、やはり耐候性、密着性、樹脂量などトータルに考えて、
弱溶剤2液型塗料が良いということは間違えようのない事実となっています。以上のことから美匠では、
外壁や屋根、雨樋などの付帯部にまで全て
弱溶剤2液型塗料を使うことを徹底しているのですが、この2液型塗料の最大の欠点としては、
先ほどもお話したように
『2つの液体(主剤と硬化剤)を1gも間違えないようにする』
ということを行っている業者は、2液型塗料を使っている業者の
全体の2%以下であると思われます。実際に2液型塗料を使っている業者の中でも、
「目で見て感覚的に調合している」という業者がたくさんいるのです。。塗料の横に秤(はかり)を置いて
いかにも秤を使って塗料を作っていると思わせておいて、
実際は感覚的に調合して作っているという業者もいるから
驚かされます。。お母さんお父さんがずっと見ているわけにはいきませんので、
対策としては、調合している写真を撮影してもらうことや、
施工後に塗料の主剤と硬化剤の残量を測り比率が合っているかの確認をする
などの対策がありますが、「そこまで業者にさせてしまってはかわいそう」
「選んだ業者を信用して任せたい」と思われるお母さんお父さんもいらっしゃると思いますので、
次回は、もっと簡単に、一つのことを確認するだけで
キッチリと施工する業者かどうか見極める方法について
お話したいと思います。最後までお読み頂き、ありがとうございました。
お母さんお父さんに少しでもお役に立てれば幸いです♪一級塗装技能士/塗料開発技術者
初代代表親方 高橋 誉